12/12 鑑と鏡 11/11 学力考査 10/10 こころで感じること 09/09 「唄の力」と言葉の持つ力 08/08 半月と直線 07/07 化学変化と物理変化 06/06 しあわせのかたち 05/05 指導と教えること 04/04 余裕 03/03 ほうれん草といかのおすし 02/02 相似な図形 01/01 類推
15/12/12
鑑と鏡
漢字の作りはよくできていると思います。「看護師」や「看護する」の『看』という漢字は,「手を目の上にかざして,注意して見る」という成り立ちがあるようです。具合の悪い患者の様子を見るとき,生半可でみて貰っては困ります。「明るい」や「明朗」の『明』の字は『日』+『月』で出来ています。『日』は太陽を表す文字ではなく,窓を表す文字『冏(けい)』のようで,これと月を表す漢字で出来ています。すなわち窓から差し込む月明かりのことを意味します。その他ほとんどすべての漢字にはその成り立ちがあり,それゆえ漢字は世界的に見ても美しい言語であるという説もあります。こうした漢字の成り立ちを知っていれば,忘れてしまった漢字を思い出す切っ掛けになります。
『躾』という漢字は「自分の身だしなみを美しくする」という成り立ちがあるようです。『躾』は中国から伝わった漢字ではなく日本で考案された漢字,すなわち国字です。日本人らしい美しいことばだと思います。さて,その躾をこどもに教えるのは親の責任であると言われます。躾が身につく時期が幼少の頃から始まるのですからそれも当然の考え方でしょう。挨拶をする,お礼を言えるなど,もしかしたら躾以前の行いなども親に依るところが大きいでしょう。こどもの成長のどの段階できちんと躾を教えられるか,それは親のひとつの資質だと思います。こどもが成長すると共に,躾の差は歴然としてきます。学校のように集団で同じ年齢の生徒が集まる場所などでは,きちんと出来る人と,そうでない人はハッキリしていくことでしょう。靴をきちんとそろえる,戸を最後まで閉める。机の中にゴミを残さない。注意されて言われれば大抵のこどもは守ります。けれども,残念ながらその場だけであることが多いのです。また少し時間が経てば,同じことを繰り返してしまうことを多々目にします。
幼少時から小学生低学年くらいまでに身につけられなかった躾を,ある程度成長してから直すのはなかなか難しいようです。でも,それを放っておくのはいかがなものでしょうか。躾を直すのに遅すぎることはありません。それを正すのは周りの大人たちでしょう。もっともその大人が模範を示せないのでは話になりません。まずは自らを正すところから心掛けることです。こどもをみればその親も見えてきます。親は子の鑑であり,子はその親の姿を映し出す鏡でもあるのです。
15/11/11
学力考査
生徒のふだんの授業や学習による定着がどの程度なのかを計る方法として学力考査があります。いわゆるテストです。学力考査にも何種類かあります。一番大きいのが中間試験や期末試験など,定期考査と呼ばれるものです。学生・生徒にとっては最も怖れるもののひとつではないでしょうか。この結果如何で自分の評価が決まります。良い結果ならば嬉しかったり誇れたりしますが,さんざんな結果に終われば親からは叱られ,先生からは厳しい指導があったり,課題が出されたり,講習に呼ばれたりもします。その時代を過ぎた大人にとっても定期試験という言葉は,未だに心地のいい響きではないかもしれません。
学力考査は定期試験ばかりではありません。日々の成果を計るため,あるいは短い範囲や単元ごとにその進捗状況をみるための小テストや,授業中に行うワークなどがあります。先生によっては抜き打ちテストをして,生徒から反感を買ったり悲鳴を上げられたりすることもあるでしょう。けれども,こうした短い範囲での確認は大切な指導だと思います。いま学んでいることを,教えている先生自身でチェックするのですから。
ところが定期試験の結果がアンバランスな先生が居ます。試験結果の点数分布が極端に偏ってしまうケースを目にします。ひとつは平均点が異常に高く,成績の分布が高得点に偏る場合です。具体的には,100点満点の試験で平均点が90点前後で,80点以上の生徒が全体の9割以上占める,といった具合です。平均が高く多くの生徒は喜ぶでしょう。親も点数だけを見て「うちの子は頑張ってる」などと勘違いするかもしれません。果たしてこの試験問題を作成した先生は良い先生なのでしょうか。一方で極端に平均点が低く,最高点でさえも70点台という学力考査もあります。平均点が20点台で30点以下,いわゆる赤点が試験を受けた生徒全体の半分を超すといったたぐいの試験です。その教科が苦手ながらも,一生懸命努力した生徒の点数が一桁になってしまうこともあります。
学力考査は学校の授業で学んだことを,それを教えた先生が作成した問題で評価をします。生徒が学んだことを正当に評価する義務が先生にはあります。先生が生徒より学力的に勝っているのは当たり前のことです。先生の力を生徒に見せつけるのは,ふだんの授業の中ですれば良いことでしょう。平均点が高い評価では,その教科を得意とする生徒にとってはまったくありがたくない話です。それほど努力をしていない生徒と,ふだんの学びをきちんとしている生徒の評価がほぼ同等になるからです。一方,どんなに頑張っても低い評価しかされなくなったらどうでしょうか。何度かは努力しても,そのうち「どうせ頑張っても大して変わらないや」と投げやりになりかねません。授業で学んだこと,自ら覚えたこと,問題練習を何度も積んだこと。こうしたことがある程度は評価されてこそ生徒は試験で出来た喜びを味わい,しくじってしまった問題を悔しがり,次こそは頑張るんだと学ぶことでしょう。そんな気持ちを起こさせる。それが先人=先生の努めだと思います。
15/10/10
こころで感じること
今年のノーベル賞は生理学・医学賞と物理学賞の二つで日本人が受賞をしました。この内の物理学賞は東京大学宇宙線研究所の梶田教授が受賞しました。物理学賞を受賞したことと同時に,その内容が報道で知らされますが,化学賞と並び内容の難解さは毎度感じることです。今回の受賞においては「ニュートリノに質量が存在したことの発見」です。物理を学んだことのない人にとっては「ニュートリノって何」と思ったことでしょう。そもそも大学で学ぶ理数系の内容は,その学科を専門としている学生にとっても,研究内容が自分の専門分野でなければきちんと理解できないでしょう。ましてやその学問と何の関わり合いを持たない人にとってはなおさらでしょう。それを承知の上で,少しだけ,本当にほんの少しだけ専門的なことを記します。ニュートリノは極小と考えられた原子よりもさらに小さい物質でその存在自体は比較的最近知られました。どんな物質も通り抜けてしまうほどの小ささです。地球であろうと人体であろうと通り抜けるのです。それほど微小な物質を観測し,その質量の存在までをも証明してしまうことは,神の領域に達してしまったのではないかと思う向きもあることでしょう。
科学の世界で起こっている事実の多くは,実際の人間の目で見ることが不可能なことが多いのです。ニュートリノよりはるかに大きい - とは言うものの相当小さい物質ですが - 原子でさえも,電子顕微鏡でないと人間は見ることが出来ません。化学反応式も中学校や高校で学びますが,その反応自体を目の当たりにするのは難しいでしょう。細胞の模式図なども,教科書や資料集ではカラフルに色づけされていますが,実際に多くの細胞は肉眼で見ることが出来ません。宇宙の始まりや,存在がにわかに信じがたい反物質など,我々の人智や想像を超えた事実が存在するのです。科学的な見地に乏しかったりすると「本当に存在するのか?」と疑ったりもするでしょう。確かに以前は正しかったことが後に間違っていた,という史実もあります。けれども現代の発達した機器類や実験設備を用いて,正しい科学的な検証を行っている現実を考えれば,そうそう間違うことはないでしょう。
大切なことは自らのこころで感じることです。想像するこころを失っては,そこから新しいモノは生まれなくなってしまいます。どんなに突拍子もないことでも,考え検証していくことが大事なのです。検証の仕方は実験設備が整っていなくても出来ます。人間の想像力には無限の可能性が秘めているのですから。科学的なことでなくてもいいのです。日常の生活の中で起こる現象,たとえば身近な人の行動や,日々の通学・通勤路での出来事。学校の先生のクセや仕草。そんなところにも新たな発見があります。寝転がっているとき,天井付近を飛んでいるハエを見て,その軌跡を方程式に表せないだろうか?,と考えた数学者が居たそうです。対象は何でもいいのです。観察する目と検証するこころを持ち続けてください。こころで感じることが大切なのです。それがいつかは真実を見極める眼力に繋がるかもしれないのですから。
15/09/09
「唄の力」とことばの持つ力
「唄の力」という言葉があります。唄には歌詞とメロディーがあり,そのメロディーに乗せてことばを伝え,人に感動を与えることが出来るのです。単に歌詞あるいは詩だけよりもメロディーをつけることによって,歌詞に抑揚がつき書いた人の気持ちを訴える力が増すのです。同じ人から同じ話を何度もされると「またこの話かよ」と嫌うことがあるものです。けれども好きな唄なら何度聴いても感動するものです。コンサートに行き,感極まって涙を流す人も居ます。それまでに何度も何度も聴いてきたはずの曲であるにもかかわらず。その感動を引き出すのは,歌詞とメロディーそして聴く人の感性やその時々の環境,あるいはその人が置かれている状況によるものだと思います。同じ曲を聴いても,感動の度合いが異なることだってあるでしょう。歌詞の内容が『いま』の自分に重なり共感を得,感動するのでしょう。
唄の半分を担う歌詞はことばです。そのことばの持つ力は大きいのです。歌詞カードに書かれた歌詞であっても,ネット上で検索して見つけた歌詞であっても,それを単に「文章」として読むのではなく,頭の中で自然とメロディーをつけて歌っているのではないでしょうか。唄によることばの持つ力の強さを感じます。時には救われ,忘れていたもの,忘れかけていたものを取り戻すことがあります。自分ではうまく表現できないことばを,気持ちを代弁してくれるような歌詞に出会ったことのある人なら,きっと感情が揺さぶられる思いを抱いたことでしょう。ずっと探していたことばにようやく出会えた,そう感じる瞬間があればその人はきっと幸せなのだと思います。
歌詞は書けなくても人に気持ちを伝える手紙は書けるでしょう。あるいは授業のさなかにノートの端に書いた散文にも言葉の持つ力を感じることがあります。手紙自体はもちろん,読む相手に思いを伝えるために書くのであれば,読み手には何かしらの思いが伝わるはずです。けれどもそうしたことを意識せずに書かれた散文にも優れたものがあります。ことばは救いであったり,呪文であったりします。あるいは取り返しのつかない状況を作ってしまうことがあります。それが意図されていようがいまいが。ことばは人だけが持つ偉大な道具であり武器でもあるのです。だからこそ強い言葉を持つ人は優しい気持ちで使わなければならないのです。相手を癒やすことも出来れば,限りなく傷つけることだって出来てしまうのだから。それを知って傷つける人は悲しい人だと思います。それを知って人に感動を与える人は『希望』だと思います。
15/08/08
半月と直線
太陽をはじめとする多くの天体は球形です。けれどもそのほとんどの星は肉眼で球体であることを確認することは困難です。よほど視力のいい人でもひとつの点にしか見えないことでしょう。肉眼ではっきりそれが球形であると確認できる天体に月があります。月は太古の昔,地球が誕生して間もない頃から存在していたと言われます。その月も周期的にその形を変えながら人の目に映ります。いわゆる月の満ち欠けです。月よりも圧倒的な存在の太陽も球形です。月と太陽の構造的な違いはいくつもありますが,大きな違いのひとつには星の成り立ちが固体であるか,気体であるかでしょう。月はアポロの月面着陸の映像を見ても分かるように『地面』が存在します。一方,太陽はそのほとんどが水素ガスとヘリウムガスで構成されています。不可能でしょうが,もし太陽に到達できても着陸する場所はないのです。
多くの恒星も月も,その形状はほぼ球体を成しています。そこに直線は存在しないのです。天体に限らず,自然界のモノたちは曲線を帯びている方が圧倒的に多いようです。直線はどこか人工的に感じてしまうことさえあります。でも,そこにある直線は本当に「真っ直ぐ」なのでしょうか?定規と鉛筆で大きめの紙に直線を引いてください。その紙を丸めて輪っかにした方向から見たら目にはどう映るでしょうか。望遠鏡をのぞき込むような方向から見るのです。見事な円になっていないでしょうか。「そんなのインチキじゃないか」という人も居るでしょう。ではその紙を元に戻しさらに直線を引き続けてみてください。実際にそれほど大きな紙は無いでしょうから,想像の上で構いません。ひたすらずっと引いていくと,地球を一周して元に戻ります。さて,その長い直線を月の上から見たらどんな線に見えるでしょうか。机の上だけで見ていた「直線」も視点を変えると曲線になるのです。要は長いか短いかの違いなのです。完全なる直線は現実には存在しないのかもしれません。
けれども,そんな形而上学的な話は置いておくとして,自然界に存在する直線を探してみました。ありました。それは夜の空に浮かぶ半月です。ちょうど半円となった月は,その直径が月の弦となり見事なまでに空を真っ二つに分けます。直線は夜の空の大きさから比べれば短いのですが,半月の弦はそこに留まらずどこまでも続いているように見えたのです。その直線によって二つの世界に分けられた宇宙がそこに存在するのだと思いました。球体である月が,太陽の光とそれを見る人間の目と想像力によって作り出された数少ない直線なのです。「それは人間の目の勝手な解釈だ」と反論する人も居るでしょう。でも,モノを見て何かを感じそこから創造できるのは人間だけでしょう。見えないものは存在しない,そんな『シュレディンガーの猫』的な考察をするのではなく,自らの目を信じてその直線を認識してほしいのです。夜空に浮かぶ直線。それを見ることができる機会はそうそう多くありません。満月を見ることより難しいかもしれません。でも一つだけ疑問点があります。それは宇宙の形状です。もし,宇宙全体が球体であるのなら,上弦によって引かれた直線も,紙の上の直線同様戻ってきてしまうかもしれません。それを「宇宙の外」から見ることができたら……。そんなことに考えが及ぶと,これはもう神の領域の世界になるでしょう。でもヒトの想像力も際限がありません。夏の夜にゆっくりと勝手な想像で創造を巡らすのも悪くないでしょう。
15/07/07
化学変化と物理変化
若者の話しことばを聞き「昔と比べると言葉が乱れている」と,しかめっ面をしながら批判する大人が居ました。一方「どの時代をもとにして『乱れている』のか」という意見もあります。ことばは常に変化しているので,どこか特定の時期を基準にすることなど出来ないという考えです。単に「乱れている」と嘆くよりも説得力があります。こうした変化はことばだけではありません。近年言われ続けている地球の温暖化や,あるいはごく最近の我が国では火山が活発化してきているなど,気候や自然界の変化の巡り合わせに私たちは出会っているようです。変化することの善し悪しは,それに遭遇する人の環境やタイミングによるものでしょう。同じような変化でも,それがいい方向なのか,本位でないものなのかはその時々に依ります。
中学校や高校で学ぶ理科の中には「化学変化」と「物理変化」ということばがあります。どう違うのでしょうか。それを考える前に,化学や物理とはどんな学問かを知る必要があります。ひと言で言うのは難しいのですが,化学は「物質の変化」に関する考察をします。一方,物理は「物体の変化」に関する学問です。では「物質」と「物体」の違いは何か,などと考えていくと,分からないことばを辞書でずっと調べていくのと同じようになるので,ここではこれ以上深追いはしません。物質の変化とは物質そのものの持つ性質を学ぶことです。一方,物体の変化とは物体そのものがどのような状態変化を持つかということです。これでは分かりにくいですね。たとえば水。水を電気分解すると,その成分である水素と酸素になります。この変化が「化学変化」です。水という状態からまったく別の状態の『物質』に変化します。一方凍らせた水,すなわち氷を砕く変化,これが「物理変化」です。氷そのものの性質は変わらず,氷の塊が小さく砕かれ『物体』が変化をします。あるいは鍋の水を沸騰させると水蒸気になります。これも「物理変化」の一例です。たとえば紙。燃やして灰になるのが「化学変化」,破いて紙くずにするのが「物理変化」です。
化学変化・物理変化のいずれにも「可逆変化」と「不可逆変化」があります。化学変化におけるこれらの変化はやや専門的な話になりますが,性質の異なるものになった「物質」がまた元に戻ることができる反応です。不可逆変化は例えば温泉などで変色してしまった指輪などが元に戻らないような変化です。物理変化の方が分かりやすいでしょう。水蒸気を瓶の中に溜め,それを冷ませばまたもとの水に戻ります。けれども粉々に砕け散ったガラス製のコップは元には戻りません。前者が可逆変化,後者が不可逆変化です。砕け散ったガラスコップを元に戻すことは出来ないでしょう。けれども,テーブルから落ちたコップが運良く割れずに済めば,それをもとのテーブルの上に戻すことは出来ます。物質と物体の変化でも,戻せる変化もあれば戻せない変化もあります。人の世に目を向ければどうでしょうか。マクロ的な視野では政治的なこと,経済に関することさまざまです。取り戻すことが可能なうちに和解したり修復できればいいのですが。ミクロ的にはそれぞれの個人が持っている悩みや人間関係,あるいは勉強や仕事に関する問題。さまざまです。今現在,自分の直面している問題は可逆変化なのか,不可逆変化なのか。冷静に見渡して判断することが大切なのです。人間の思考は自由に発想できます。間違えに気づけば引き返すことだって可能なのです。思考の変化は柔軟で一方通行ではありません。そんな可逆変化の存在を信じて,固執した考えからの脱却もあり得ることなのです。
15/06/06
しあわせのかたち
その昔,JRがまだ国鉄だった時代のこと。特急列車がはじめて走り始めた頃,鉄道の同好の士が特急列車に乗ったところ,国鉄の職員に「なぜ特急は普通列車よりも運賃が高いのか」と訊いたそうです。質問の意図が飲み込めなかった職員に彼はこう説明したそうです。「乗っている時間が短いのに,何で料金が高いのか」と。彼にとって列車は移動手段では無く,乗って楽しむものだったようです。目的地により早く到着することの方を良しとする観点からは,到底発想できないことでしょう。
高齢者に何が一番欲しいかという質問をしたところ,何と答えたでしょうか?孫との楽しい時間,あるいは美味しい食事,それとも使いやすい家電製品でしょうか。確かにそういったものを欲する人も居るでしょう。でも,現金が欲しいというお年寄りも案外多いようです。確かにお金があれば,孫に贈り物をしてあげられるし,贅沢な食事も出来れば,高機能の家電製品だって買えます。宝くじで高額当選をした人に配られる本があるそうです。その中には遺言書を書くことも指南されています。あまり気分のいい話とは思えません。実際のところは知りませんが,高額当選者が不幸になった事実があることはときに耳にします。宝くじで不意に大金を手にした人は幸せなのでしょうか。それとも不幸の始まりなのでしょうか。
しあわせのかたちは人それぞれだと思います。のんびり列車の旅を楽しむ人。時間を惜しんで高くても飛行機で移動する人。お金を出してレストランで絢爛豪華な食事をする人。自分で食材をそろえ,手間暇掛けて料理する人。どちらが優れているとか裕福であるとか,それ自体比較するのはいかがなものでしょうか。まったく会話の無い2人が喫茶店に入り,ゆっくり備え付けの雑誌を楽しむのと,相手のことに気兼ねして無理矢理会話を探して20分ほどで店をあとにする2人。傍目には会話の無い2人は仲でも悪いのかしら,と思われるかもしれません。楽しげにテーブルを挟んで会話をしていた2人は,一時間もしないうちにその内容のことなど思い出せないかもしれません。なにがその人の幸福度を測れるのでしょうか。それを測るひとつの尺度があるようです。たとえば幸福度の高いものには試験に合格する,仕事で成功を収める,こどもが生まれるなどです。逆に不幸の度合いが高いものは身内の死,病気や怪我をするなどがあるそうです。確かにこういった類いのものは共通していることなのでしょう。けれども人のもの差しはそれぞれ違うものです。他人のもの差しで自分のしあわせは測れないし,測って欲しくも無い。そう感じるのが当然でしょう。日々の生活の中で,何にしあわせのかたちを求めるのか。それこそ自分の尺度で測るべきことなのです。
15/05/05
指導と教えること
先生が生徒に教える授業にはさまざまな形態や手法があります。それぞれの先生が授業に工夫を凝らしたり,教材に手を掛けたりします。もちろんすべての先生が同じようにしている訳ではなく,場合によってはそういったことを意図してなのかは分かりませんが,手を抜いている先生も居るようです。もちろん,そうした先生は少数派であると願いたいものです。学校の先生でも,塾や予備校の先生でも,その中に必ず人気の先生が居ます。学校では先生が違うだけで,同じ学年の同じ試験で平均点が異なってしまうことがしばしば見受けられます。基本的に学校の先生は,教わる生徒側で選ぶことが出来ないので,運・不運が作用することがあります。たくさんの人間が居る中で起こることだし,誰でも最初から教えるのが上手であるとも限りません。平均点が低いクラスを受け持った先生は,自分の指導のどこが足りなかったのかを反省して,次へと繋げればいいのです。団体競技のスポーツでは,監督が替わっただけでめざましい躍進を遂げ,すばらしい結果を残すということをよく耳にします。指導者によって選手の才能を引き出し結果を残すいい例でしょう。
教えることは難しくはありません。でも,生徒を指導することは簡単ではないのです。知識で生徒を圧倒できるのは先生なら当然のことでしょう。それをひけらかしたり上段から構えて見下しても生徒はついて来ません。指導するには知識も必要ですが,教える技術と準備する労力,そして何よりも教える教科を愛し,情熱を持って生徒に接することでしょう。教材準備もソフトで素早く作るばかりではなく,その都度生徒のレベルや目的に適した選択が必要なのです。適した問題がなければ自分で作る。既製の問題で対応できないならばそうするのが正しい道でしょう。それが出来るからこそ『先生』なのです。生徒の先を歩いてきたのですから。
教えすぎるのではなく,生徒自ら考えさせる。指導するためには,そうした我慢強さも必要なのです。受け身的な授業は生徒は楽でしょうが,教える先生はもっと楽でしょう。学校の先生に対して評価が低い授業のひとつに,教科書をそのまま写しているのと変わらない授業があります。それに気づいた生徒はやがてノートを取らなくなり,授業への興味も失せ聞かなくなります。生徒にとって,これほど不幸なことはありません。いにしえの古文に馳せた思い,大統領のすばらしい演説,感動的な図形。それらに出会うタイミングを奪うのは,導くべき先生なのかもしれません。先を走るものには伝えるべきことをしっかり伝える義務があることを胸に刻んでおくべきことなのです。
15/04/04
余裕
時間に追わながら勉強や仕事をすると,決まってどこかでほころんで失敗したりするものです。学生の勉強なら試験という締め切りが,社会人ならば会社や上司,あるいは取引先相手によってその締め切りが決められるのでしょう。時間制限があるからこそ,ひとつの結果を出すことが出来るわけで,これがなければダラダラと時間を過ごしてしまうのが道理でしょう。中にはそうしたこととは無縁の人も居るかもしれませんが,それはかなり希な方でしょう。時間に余裕がなくなると,どこか省かなければなりません。あるいは作業が雑になったり,本来あるべき姿から遠ざかったりもします。
福岡にある会社の新入社員研修で,太宰府天満宮まで往復をし,その後にレポートをさせるというものがありました。それを言い渡された新人たちは,慌てて書店に飛び込みました。太宰府に関する書物を買ったのです。そしてその往復の車内で本を読み,太宰府に関する知識を詰め込んだのです。会社に戻って上司の面接を受けた新人は唖然としました。聞かれたことは往復での沿線の情景だったのです。新人は誰一人として窓の外の景色に目を向けようとしなかったのです。時は春真っ盛り。たくさんの桜が咲き誇っているその絶景。それさえも楽しむ余裕がなかったのでしょう。ほんの少しの間でも外の風景を楽しめる瞬間があってもよかったのに。
幹線道路を車で走っていると,何をそんなに急いでいるのかしら?と首を傾げたくなるような運転をしている人を見かけます。ゲームでもしているかのように,車と車の隙間を縫って通り過ぎるのです。果たして彼にはそれほど時間がないのでしょうか。車から降りると,すぐに仕事に取りかかるのでしょうか。おそらくそこまで切羽詰まった人は希だと思います。急ぐあまり事故でも起こしてしまったらそれこそ時間の無駄でしょう。その事故も自損だけならまだしも,他人を巻き込んでしまったら悲しいことです。ほんの少し早めに行動が出来ていればと思うのです。
仕事が忙しく,次から次へと処理していかなければならないことがあります。勉強をしていて,あれもこれもやらなくちゃと焦ることがあります。でも,そんな状況でさえちょっとしたユーモアを持った遊び心があってもいいと思います。本当に追い詰められることなどそうそうないはずです。笑い飛ばせるくらいの度量があれば,大抵のことは乗り越えられるはずなのです。そんな余裕が新たな発想に繋がることもあるのだから。
15/03/03
ほうれん草といかのおすし
大切な事柄を忘れないため,あるいは常に心がけるために,標語を持って意識することがあります。ビジネスマンは仕事をする上でさまざまな処理しなければならない出来事があります。取引先へサジェスチョンしたり,お得意様に案内を出す,あるいは新たな客層を切り開く,店のディスプレイを常に新鮮なモノにする。学校関連でも教務もあれば授業準備や行事予定の作成,部活での生徒指導にPTAの準備など数え切れないほどの要素が詰まってます。そんな煩雑な中でも,きちんと守らなければならないことがあります。けれども日々の雑多なさなか,つい忘れてしまうことだってあるでしょう。ビジネスで使われるものに「ほう・れん・そう」があります。これは証券会社の社長が車内キャンペーンではじめたもので,「報告・連絡・相談」を分かりやすくするためにほうれん草に掛けた略語だそうです。上司への報告をし,部下の相談に乗ることで会社を強くするために考えた言葉なのです。「ほう・れん・そう」の可否を問うこともありますが,会社の発展を切に願う社長の思いは伝わります。
こども達を痛ましい事件から避けるために「いかのおすし」という標語が9年ほど前に誕生しました。小学校低学年を中心としたセイフティー教室でこども達に教えているようです。覚えやすい標語でしかもインパクトの強い言葉を考えたようです。こどもに馴染みやすい言葉で効果が期待できるでしょう。実際,ここ最近でもこの標語のお陰で難を逃れたというニュースがありました。親の目を離れたこどもは,悪意を持った大人の前では無力で,とうてい太刀打ちなどできないのです。24時間いつでも目が届くものではありません。そんなこども達が自らの身を守るために,大人が考え出した標語は今や全国的に浸透しているようです。この標語は犯罪をもくろむ輩の心理を突いていて,かつこどもにできる防御法が含まれていて,秀逸だと思います。
行動を促すのに何かの言葉が役に立つことがあります。背中を押してくれるひと言。やる気スイッチを押してくれる言葉。それをふだんの生活の中に取り入れたのが標語でしょう。「ほう・れん・そう」や「いかのおすし」に匹敵するくらいの個人的な標語は何でしょうか?それは個々が持つ標語でもあり,自ら考案するのがいいのかも知れません。座右の銘とは一線を画した標語は,自分自身に掛けるべき言葉であり,それは生きていく中でのひとつの羅針盤になることでしょう。
15/02/02
相似な図形
数学には「相似な図形」という言葉があります。「相似」の定義にはいくつかありますが,ここでは簡単に「同じ形をしたもの」と考えてください。代表的なものとしては小中学生が授業で使う三角定規があります。三角定規には二種類あって,ひとつは45度が2つと90度の直角二等辺三角形,もう一つは30度と60度それに直角である90度の三角形です。どちらの三角形も,大きさこそ違えすべて相似です。鞄に入っている三角定規も,先生が黒板で使う大きな三角定規もすべて同じ形をしています。他にはどんな図形が相似でしょうか?代表的なものは「円」と「球」それに「正方形」と「立方体」でしょう。すべての円,すべての球がそれぞれ相似であることは誰にでもすぐに理解できることでしょう。正方形や立方体に関しても同様でしょう。縦と横,立方体なら高さを含めすべて同じ長さのものを同じ比率で拡大もしくは縮小すれば,新たに出来る図形も正方形もしくは立方体になることは,きちんとした証明を見るまでもないことです。
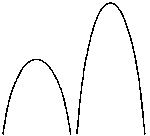 さて,これらに比べるとすべての「放物線」が相似であることは案外知られていません。放物線はその文字の通り,ものを投げたときに描く軌跡です。中学・高校の数学で学ぶ「二次関数」がそれです。放物線には大きく開いたものもあれば,先端がとがったような形もあります。一見するとどうしてこれが同じ形なのかと思う人もいるでしょう。けれども数学的にはきちんと「相似」であることは証明されています。円や正方形と比較して,放物線が異なるのは『終わり』がないからでしょう。円や正方形はひとつの『閉じた』平面の中にあります。球に関してもやはり『閉じた』空間に含まれています。ところが放物線はどうでしょうか?どこまでもその美しい曲線は続くのです。教科書や問題集では紙面に限りがあるためどこかで『終わり』を作らなければならないのです。実際はどこまでも続いているのです。その意味ではすべての「直線」は「相似」な図形です。数学の概念では,直線は始まりもなければ終わりもありません。
さて,これらに比べるとすべての「放物線」が相似であることは案外知られていません。放物線はその文字の通り,ものを投げたときに描く軌跡です。中学・高校の数学で学ぶ「二次関数」がそれです。放物線には大きく開いたものもあれば,先端がとがったような形もあります。一見するとどうしてこれが同じ形なのかと思う人もいるでしょう。けれども数学的にはきちんと「相似」であることは証明されています。円や正方形と比較して,放物線が異なるのは『終わり』がないからでしょう。円や正方形はひとつの『閉じた』平面の中にあります。球に関してもやはり『閉じた』空間に含まれています。ところが放物線はどうでしょうか?どこまでもその美しい曲線は続くのです。教科書や問題集では紙面に限りがあるためどこかで『終わり』を作らなければならないのです。実際はどこまでも続いているのです。その意味ではすべての「直線」は「相似」な図形です。数学の概念では,直線は始まりもなければ終わりもありません。
すべての直線が相似であることは比較的容易に理解できると思います。どんな直線でも,重ねてしまえば一緒です。「太い縄の上に糸を置いても,きれいに重ならないじゃないか」と反論する人がいるかもしれません。でも,数学における「直線」は『太さ』をもちません。その点を含んだ上で考えてみてください。そうすればすべての直線が相似であることは理解できるでしょう。同様に『終わり』の無い放物線も,大きな放物線のほんの一部なのです。数学的な計算による証明よりも,類似する簡単なもの(ここでは直線)から複雑なもの(放物線)へと考え方を移行することで,困難な問題や命題も理解しやすくなります。身の回りのこともちょっと距離を取り,簡単なことに置き換えてみてはいかがでしょうか。案外先が開けるかもしれません。
15/01/01
類推
暗号にはさまざまな種類があるようです。例えば簡単につくれる一例として,数字と文字を対応させるものがあります。「a1b4g1c2d4a5g44dd5a3」は「あけましておめでとう」となります。「abcde…」が「あかさたな…」の行を,数字が「あいうえお」の段を表します。「4d」のようにアルファベットと数字を入れ替えたものは濁点を意味します。文字をひとつずつずらす暗号作成法もあります。「いこみすとかもどなえ」となると意味不明です。さらに「いくみさとえもづない」となるとさらに解読は難しいでしょう。奇数番目は次の文字,偶数番目は前の文字にしてあります。もっと難解にする方法も考えられるでしょう。暗号文を作成する方は簡単ですが,そのルールを見破り解読するのはそれなりに知識や規則性を知らなければなりません。暗号ではありませんが,こんなクイズがあります。「T=1,D=1,F=2,K=?」です。?に入る数字は何でしょうか。一見関係性の無いアルファベットと数字の関連性を知ることが,さまざまな暗号作成の一助になることも,解読の切っ掛けになることもあります。そして,考え続けることが大切なのです。
暗号ではありませんが,パソコンなどで作るパスワードに苦労する人も多いことでしょう。どのパスワードも同じモノにする訳にもいかないでしょう。銀行のキャッシュカードのように4桁では受け付けてくれないことも多々あります。英数字を混ぜ,しかも必ず大文字と小文字を混ぜなければならないこともあります。複雑な上に忘れると厄介なパスワードに苦労することもあります。好きな詩や小説の書き出し文を使う方法もあります。例えば漱石の草枕「山路(やまみち)を登りながら,こう考えた」を「yamamichiwonoborinagarakoukangaeta」とした場合はどうでしょうか。パスワードとしてはまだ弱いでしょう。有名すぎる一文だし,すべて小文字だからです。こうしたらどうでしょうか「YamamichiwoNoborinagaraKoukangaeta」です。大文字が入った分少し難解です。さらに「Yamam1ch1w0N060r1nagaraK0ukangaeta」とすると,それなりのセキュリティは確保できるでしょう。ただ,厄介なのは複雑になればなるほど,今度はそれを覚える側が大変になることです。
解読の難しさはパスワードだけではありません。人の心のメカニズムはもっと難しいでしょう。個々人の経験することは,その人だけに存在する唯一無二の記憶です。その記憶でさえも曖昧であることは自明です。時間経過と共に劣化することは誰もが認めることでしょう。そんなたよりない存在でありながらも,人は人の言葉でその真意を類推しようと試みます。でも類推が怖く思えてしまう場合もあります。歴史上の人物の発した言葉にどんな思いがあったのか,それはまさしく類推するしか無いでしょう。その人の生い立ちや環境,その言葉を発したあるいは記したときの状況などからなぜその言葉が出たのかを類推するのです。それが研究というものでしょう。けれども,いま存在している人,しかもそれが身近な人物の場合,直接答えを得られる可能性があるだけに,類推する怖さは歴史上の人間よりも厄介かもしれません。そこには類推ではない真の答えがあるからです。
